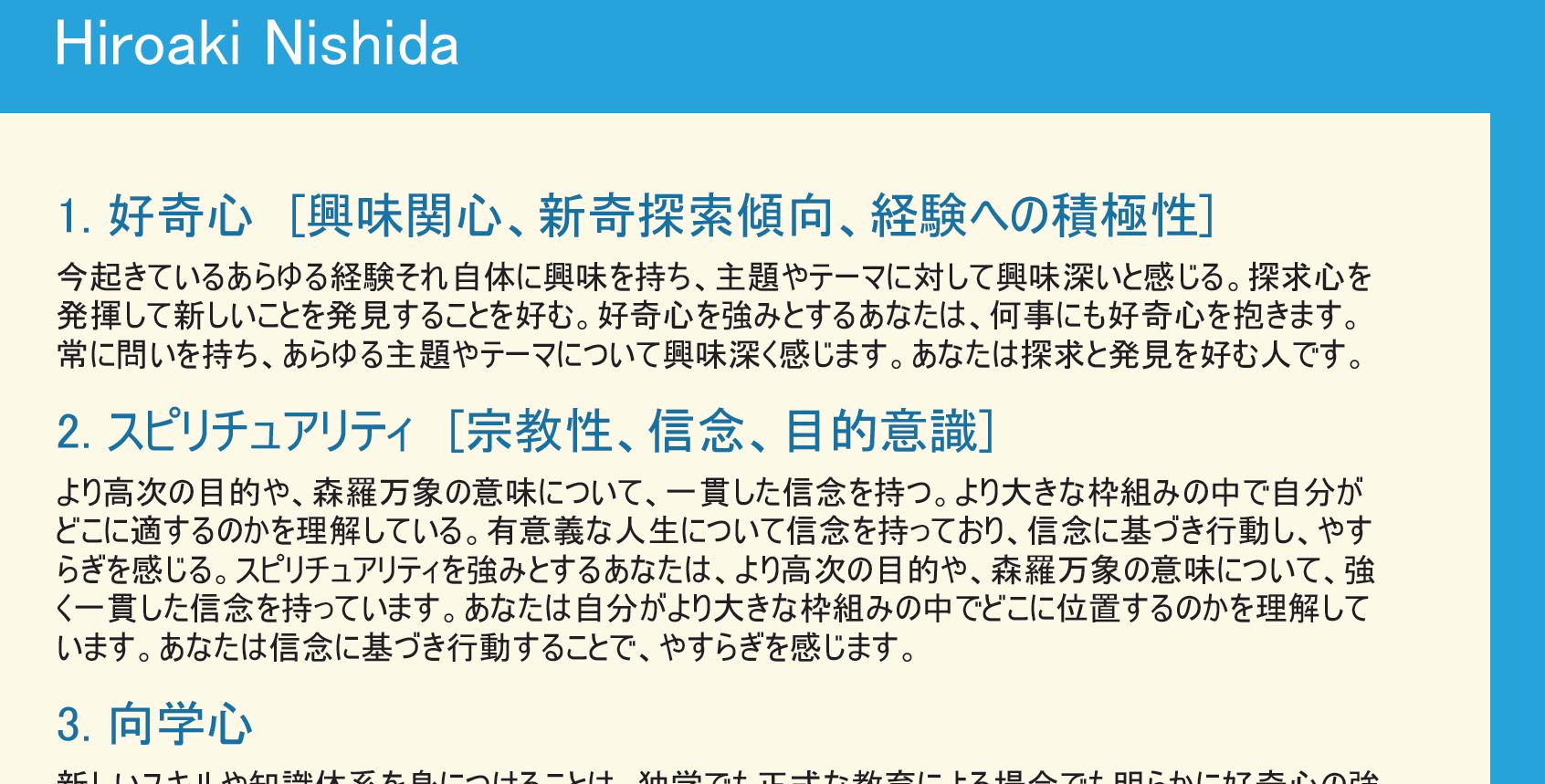時には流行に乗ってみようかと(笑)。
実は今、ミヒャエル・エンデの「はてしない物語」を読んでます。
「書店ガール」に、人生を変えた本ってことでよく出てるんだって?
俺流行に敏感ですから(笑)。
偶然だけど(笑)
初めて読んだのは10歳ぐらいかな、あれから22年ぐらい?
おそらくこれが3回目か4回目ぐらいなんだけど、
読むたびに味わいが違います。
**以下引用。改行は西田が追加**
カイロンはゆっくりうなずいてから、
金のお守りの鎖を首からはずし、アトレーユの首にかけてやった。
「アウリンはそなたに大いなる権威を授けよう」
カイロンは荘重な響きで語り始めた。
「しかしながら、その権威を用いることはならぬ。
女王様もそのご意向にものいわせることは、決してなさらぬからだ。
アウリンはそなたを守り導くであろう。
だがどんなことに出会おうとも、けっしてそれに手を出してはならぬ。
これより先、そなた自身の考えは意味を持たぬのだから。
ゆえに、いかなる武器もたずさえずに出発するのだ。
何事も起こるがままに起こらしめよ。
悪も善も、美も醜も、愚も賢も、すべてそなたにとっては区別はないのだぞ。
幼心の君の前においてはすべてが同じであるようにな。
そなたのすべきことは、求め、たずねることのみ。
そなた自身の意見にもとづいて判断をくだしてはならぬ。
よいか、決して忘れるでないぞ、アトレーユ!」
*****
アトレーユとイグラムールの会話
「一時間だと?」アトレーユは叫んだ。
「たった一時間で何ができるというのだ!」
「それでもお今お前に残されている時間よりは長いぞ。さあ、決断だ!」
アトレーユは考えあぐねた末、たずねた。
「幼ごころの君のみ名においてたのめば、おまえたちはその幸い竜を話してやってくれるか?」
「ならぬ。」顔が答えた。
「おひかり、アウリンをさげているからといって、お前にはイグラムールにそれをたのむ権利はない。
女王様はわれわれみなを、あるがままにあらしめてくださるのだ。
だからこそ、イグラムールも女王様のおしるしには頭を下げる。
これはお前にもよくわかっているはずだ。」
アトレーユは頭をたれたまま立ちつくした。イグラムールの今いったことは、真実だった。
*********
バスチアンとグラオーグラーマーン
バスチアンはライオンに宝のメダルの裏に記された文字を見せてたずねた。
「これは、どういう意味なんだろう?
『汝の 欲する ことを なせ』というのは
ぼくがしたいことはなんでもしていいっていうことなんだろう、ね?」
グラオーグラマーンの顔が急に、
はっとするほど真剣になり、
目がらんらんと燃えはじめた。
「ちがいます。」あの、遠い、遠雷のような声がいった。
「それは、あなたさまが真に欲することをすべきだという事です。
あなたさまの真の意志を持てという
ことです。これ以上に難しい事はありません」
「ぼくの真の意志だって?」バスチアンは心にとまったその言葉をくりかえした。
「それは、いったい何なんだ?」
「それは、それはあなたさまがご存知ないあなたさまご自身の深い秘密です」
「どうしたら、それがぼくにわかるだろう?」
「いくつもの望みの道をたどってゆかれることです。一つ一つ、最後まで。
それがあなたさまをご自分の真に欲すること、
真の意志へと導いてくれるでしょう」
「それならそれほど難しいとも思えないけど」バスチアンはいった。
「いや、これはあらゆる道の中で、一番危険な道なのです」ライオンはいった。
「どうしてだい?」バスチアンはいった。「ぼくは怖れないぞ」
「怖れるとか怖れないとかではない。」
グラオーグラマーンは声を荒らげていった。
「この道をゆくには、この上ない誠実さと細心の注意がなければならないのです。
この道ほど決定的に迷ってしまいやすい道はほかにないのですから」
「それは、ぼくたちの持つ望みがいつもよい望みだとはかぎらないからかい?」
ライオンは尻尾でそばの砂をぴしゃりと打った。
そして耳を伏せ鼻にしわを寄せた。
目は火を吹いていた。
つづいてグラオーグラマーンがまたあの大地を揺るがす声を発したとき、
バスチアンは思わず頭をすくめた。
「望みとは何か、よいとはどういうことか、わかっておられるのですかっ!」
************
アイゥオーラおばさん
「それからというもの、ぼうやは一つの望みから次の望みへと、
旅をして、そのつど望みが満たされていきました。
(…)
ところが、ぼうやは、望みが一つかなえられるたびに、
自分の元いた世界の記憶を、一つずつなくしていったのです。
ぼうやはもう帰る気はなかったので、気にもかけませんでした。
だから次から次へと望みを持って進むうちに、
とうとう記憶のほとんどを失ってしまいました。
覚えていることがなくては、もう進むこともできません。
(…)
ぼうやはそれでもまだ、何が真の意思なのかわかりませんでした。
いまやそれが見つからないまま、
残されたわずかな記憶までなくなってしまう危険が出てきたのです。
もしそんなことになれば、ぼうやはもう自分の世界に帰れなくなるのです。
そのとき、ぼうはや、やっと変わる家にたどり着きました。
そして、真の意思が何なのか、それがわかるまでそこにいることになりました。
というのは、この変わる家というのは、
家そのものが変わるだけでなくて、家がその中に住む人を変えるから、
そういう名前がついているのです。
それは、ぼうやにはとても大切なことでした。
ぼうやはそれまで、自分とはちがう、
別のものになりたいといつも思ってきましたが、
自分を変えようとは思わなかったからです。」